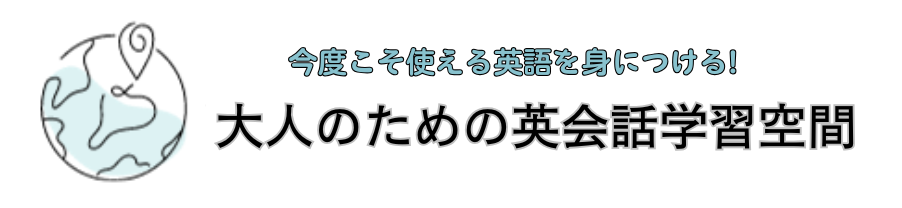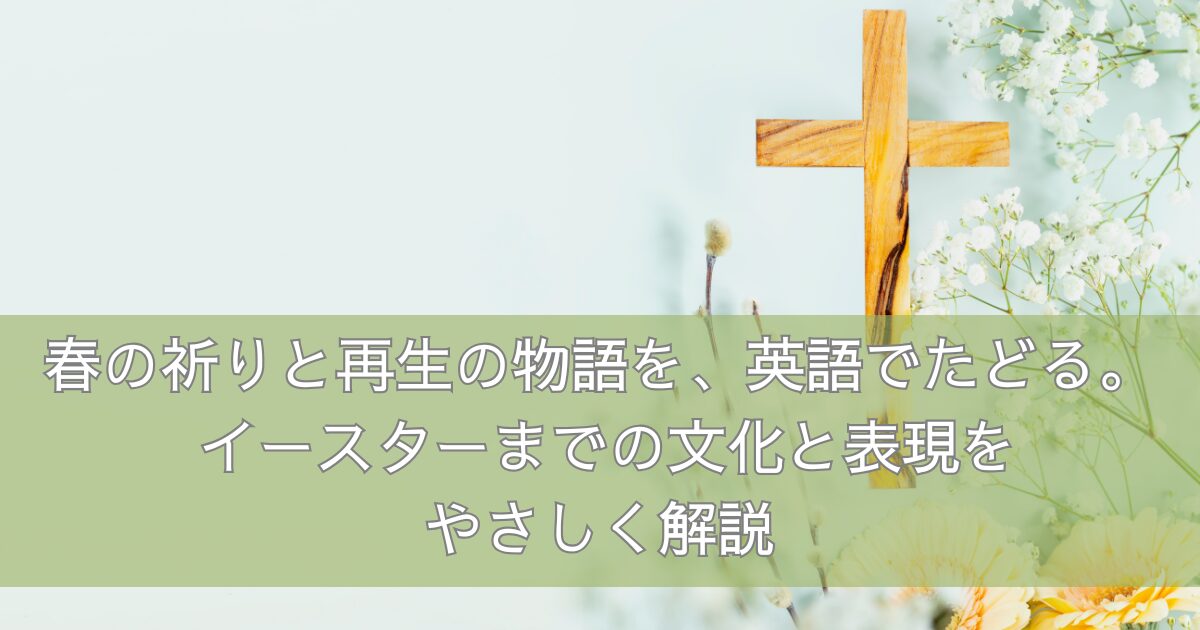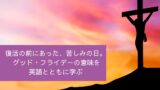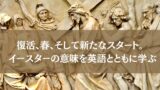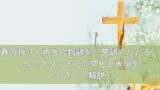「英語を学ぶなら、宗教のことも知らなくちゃいけないの?」
長く英語を学んできた方、特に海外経験のある方なら、一度は感じたことがあるかもしれません。 日本では宗教にあまり触れずに生きることもできますが、英語の背景にはキリスト教文化が深く根付いています。
このシリーズでは、イースター(復活祭)というキリスト教最大の祝日を中心に、その前後に起こる行事や背景を英語とともにたどってきました。
総集編では、春の祈りと再生をテーマに、以下の流れを振り返りながら、英語に潜む宗教的な背景や表現も改めてご紹介します。
イースターまでの流れをおさらい
- Mardi Gras(マルディグラ)|節制の前の最後の祝祭
- Ash Wednesday(灰の水曜日)|悔い改めの始まり
- Lent(レント)|40日間の節制と祈り
- Palm Sunday(パームサンデー)|イエスがエルサレムに入城
- Good Friday(グッド・フライデー)|イエスの受難と死
- Easter Sunday(イースター)|復活と希望の日
海外のイースターあるある7選|英語文化のリアルを感じよう
- 🐣 子どもたちは本気でエッグハント!(庭や公園で大はしゃぎ)
- 🐰 スーパーにうさぎと卵モチーフのチョコがずら〜り
- 🥚 茹で卵に家族で絵付けするのが定番行事
- 🕊 教会は大混雑!1年ぶりに来る人も多い
- 🌸 春らしい服でおしゃれしてブランチへ
- 🍽 食卓にはラム肉やホットクロスバンズ
- 📸 SNSには「Happy Easter!」の投稿がたくさん
もっと詳しく知りたい方はこちらの記事もどうぞ👇
👉 アメリカ・イギリスのイースターあるある7選(英語学習者向け)
英語に残るキリスト教由来の表現
英語には、宗教的なバックグラウンドを知らないと意味が伝わりにくい表現がたくさんあります。
- cross to bear:十字架を背負う→「避けられない苦しみ」
- resurrection of interest:関心の復活→イースターの「復活」から来た表現
- blessing in disguise:不幸に見えて実は祝福→「神のご加護」的な考え方
- passion project:本気の取り組み→もともとは「受難(Passion)」から
こうした表現を知ると、英語がぐっと立体的に感じられるようになります。
英語を通じて文化と祈りを知る
英語はただの言語ではなく、文化や歴史、そして価値観を運んでくれるツールでもあります。 キリスト教徒でなくても、英語を学ぶならその背景を知っておくことは大きな意味を持ちます。
このシリーズが、読者の皆さんにとって「ことばの奥にあるもの」を感じるきっかけになれば幸いです。
この総集編をきっかけに、まだ読んでいない記事があれば、ぜひあわせてご覧くださいね。
📚 イースター特集シリーズ(おすすめの読書順)
※今読んでいる記事には「(今ここ)」と書いてあります。
②うさぎと卵の意味、知ってた?イースターの不思議なシンボル解説
③イギリスとアメリカの違いも?イースターの文化的背景まとめ🇬🇧🇺🇸
⑤パームサンデーって何の日?イースター直前の大事な日を解説🌿
⑥Good Fridayって悲しい日?その意味と英語表現をやさしく紹介
⑦イースターサンデーの本当の意味とは?大人にもわかりやすく解説
⑧イースターって何?マルディグラからイースターまでの流れまとめ
🔖 この記事はシリーズの8番目です(今ここ)
他の話もぜひあわせてどうぞ!