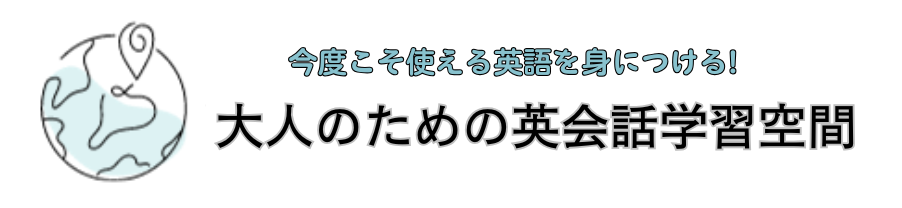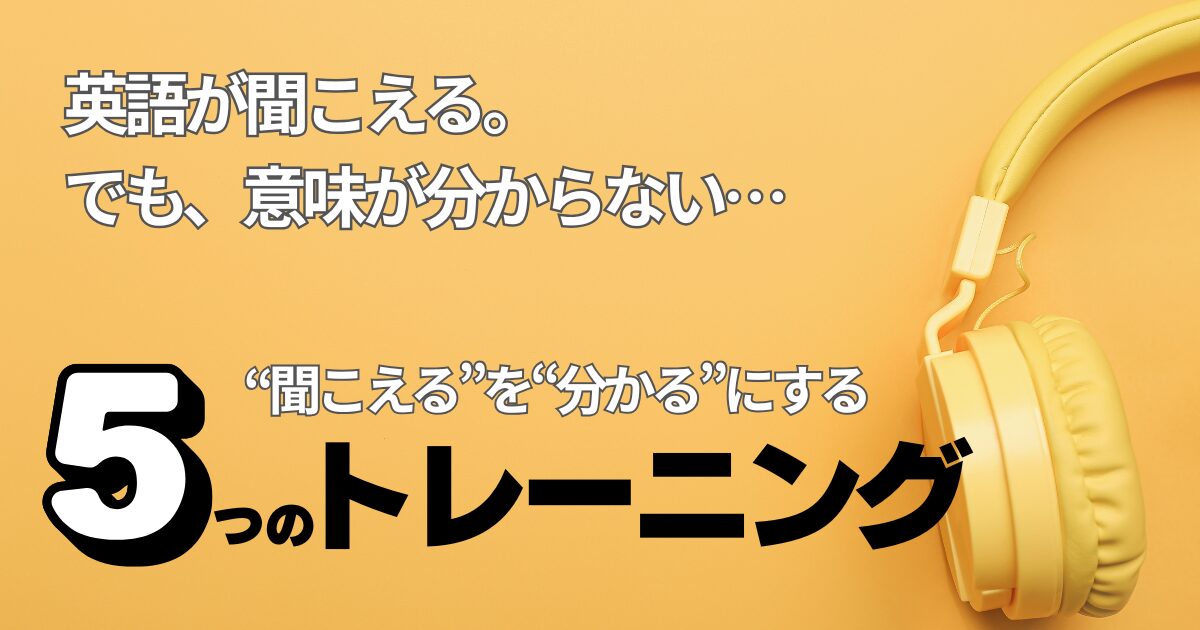英語の音は聞こえる。
単語もところどころ分かるし、前よりスピードにも慣れてきた。
だけど——
「何を言ってるのか結局よく分からない」
「話がどんどん進んでしまって、ついていけない」
そんなもどかしさを感じていませんか?
これは、英語リスニングにおける典型的な“第2の壁”とも言える現象です。
リスニングの初期段階(=音が拾えない)を超えたあと、多くの学習者が直面するのが、
**「意味処理が追いつかない」**という新たな課題です。
これは決して、あなたの耳が悪いわけでも、センスがないわけでもありません。
単に、「意味を理解する力」がまだ“耳のスピード”に追いついていないだけ。
では、どうすればその壁を越えられるのか?
本記事では、この“リスニングの壁”を突破するための具体的な原因分析と、5つの実践トレーニング法をご紹介します。
本記事は、こんな悩みを感じている方に向けて書いています:
- 単語は聞こえるけど、意味がふわっとしか分からない
- センテンスが長くなると、頭の中がごちゃごちゃになる
- 「話が進むとついていけなくなる」「結局、半分も理解できてなかった」と感じる
もしあなたが、「英語を“音”から“意味”へつなげる感覚を身につけたい」と思っているなら、この記事はきっと役に立ちます。
📌 なぜ「意味がわからない」のか?6つの主な原因
英語が「聞こえている」のに「理解できない」――
それは多くの場合、リスニングそのものではなく、“意味処理”の工程で詰まっているからです。
ここでは、リスニング中に意味が頭に入ってこなくなるよくある原因を整理してみましょう。
- 語彙力不足:知っている単語が少なければ、当然意味も取れません。
- 文法の理解不足:単語はわかっても、構造がつかめなければ意味が見えません。
- 英語の処理スピードが追いつかない:頭の中で日本語に変換している間に次の文が来てしまう。
- 返り読みの癖:英語を前から理解する習慣がなく、文末でようやく意味を取ろうとして間に合わない。
- 音声変化に対応できない:リエゾン、リダクション、弱化など、ナチュラルスピードの英語についていけない。
- 背景知識の不足:話の流れが予測できず、内容が頭に残らない。
上記のうち、1つでも当てはまるなら、理解が追いつかない原因はそこにある可能性大です。
でも大丈夫。こうした“意味処理の詰まり”は、トレーニングでちゃんと改善できます。
次章では、それぞれの原因に対応した具体的な学習法を紹介していきます。
解決法1|語彙力と文法の「意味リンク」を強化する
単語を覚えるときは、音・意味・例文の3点セットで覚えるのが鉄則。
「意味だけ知ってる単語」は、実際の音や使い方に出会ったとき、処理できません。
そしてもう一つ大切なのが文法です。
文法は、英文の「骨格」。構造がつかめなければ、いくら単語を知っていても全体の意味は取れません。
そして文法の力を、実際の英文理解に活かす読み方としておすすめなのが、「スラッシュリーディング」です。
🔎 スラッシュリーディングとは?
スラッシュリーディングとは、英文を意味のかたまり(チャンク)ごとにスラッシュ( / )で区切りながら、
英語の語順のまま前から理解していく読み方です。
例:
I went to the store / to buy some milk / before dinner.
→ 「私は行った / お店へ / 牛乳を買いに / 夕食の前に」
→ ✨ポイントは、日本語に訳さず、英語の順で“場面”を頭に描くこと!
❌ VS:こういう読み方してませんか?
日本語訳で読み慣れてきた人は、こんな“昭和リーディング”になってしまうことが多いです:
- 文末まで全部読んで
- 最後に主語に戻って
- 日本語に組み直して「つまり〜ってことか」
この“返り読み”癖があると、リスニングでも「後ろに戻る」クセが残り、
英語を前から理解するスピードがつかない=意味処理が追いつかない原因になります。
✍️ スラッシュリーディングのやり方(初級〜中級向け)
- 簡単な英文素材を用意(英検準2級〜TOEIC600レベルくらいでOK)
- 1文ずつ「意味のかたまり」でスラッシュを入れる(最初は教材に書き込んでもOK)
- スラッシュごとに「何が起こってるか」をイメージで理解(日本語にせず“場面描写”)
- 音読やシャドーイングに応用すれば、リスニング力にも直結!
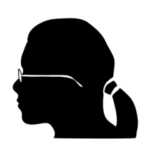
💡最初は1文ずつでもOK。慣れてくると、英語を英語のまま処理する“英語脳”が育っていきます。
解決法2|音声処理のスピードを鍛える4つの方法
リスニング中に「意味が追いつかない」と感じる原因のひとつは、英語のスピードに“意味処理”がついていっていないことです。
ここでは、音と意味を結びつけるスピードを高めるための4つのトレーニングをご紹介します。
- 音読:英語の語順で意味を追いながら読む。リズムと構文感覚が鍛えられる
- シャドーイング:意味を意識して影のように発話。処理力&音感UP
- ディクテーション:書き取りで「自分が拾えてない音」を発見
- オーバーラッピング:音声と同時に発話し、英語のリズムを体に染み込ませる
🔸 音読(Reading Aloud)
音読は、英文を声に出して読む練習です。
ポイントは、ただ読むのではなく、語順のまま意味を追いながら読むこと。
これにより、返り読みの癖を矯正し、英文の構造・リズム・語順感覚が自然と身につきます。
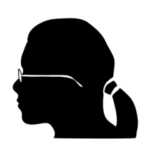
💡初めての人は、**短くて簡単な英文(中学レベルOK)**からスタートするのがコツ。
できるだけ音源のあるものを選びましょう。
🔸 シャドーイング(Shadowing)
シャドーイングは、英語音声を聞きながら、1〜2語遅れて“影のように”発話する練習です。
音を正確に捉え、すぐに自分の口で再現することで、聞く力・発音・意味処理のスピードが総合的に鍛えられます。
特に効果的なのは、意味を意識しながら行う“コンテンツシャドーイング”。
「何を言っているのか」を理解しながら真似することで、表面的な音真似に終わらず、**“聞いて理解する力”**が育ちます。
🔸 ディクテーション(Dictation)
ディクテーションは、音声を聞いて、そのまま書き取る練習です。
自分が「聞き取れたつもり」でいた部分が、実は曖昧だったことに気づかされる、非常に地味で効果の高い訓練です。
- 1文を流す → 書き取る → スクリプトで答え合わせ → 聞き直す
という流れを繰り返すことで、リスニング・スペリング・文法感覚まで磨かれます。
🔸 オーバーラッピング(Overlapping)
オーバーラッピングは、英文スクリプトを見ながら、音声と同時に発話する練習です。
ポイントは「音声に完全に重ねて話す」こと。タイミング・抑揚・スピードをネイティブとぴったり一致させるのが目標です。
これにより、英語のリズム・音声変化の感覚・イントネーションの習得が一気に進みます。
シャドーイングよりも取り組みやすいので、初心者の導入練習としてもおすすめです。
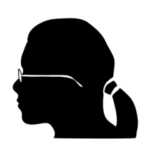
イメージはカラオケ。
カラオケは歌ですが、オーバーラッピングではセンテンスを読んでいくのです。
解決法3|英語のまま理解する「英語脳」を鍛える
リスニングで意味がつかめない原因の1つが、「日本語に訳さないと理解できない」という癖。
この“訳読クセ”があると、英語を語順のまま処理するスピードが圧倒的に足りなくなってしまいます。
ここでは、「英語を英語のまま理解する」ためのトレーニング法を紹介します。
- 日本語を介さずに理解する意識を持つ
- チャンク(かたまり)で処理する練習をする
- 英語に触れる“量”を増やして、慣れを作る(多聴・多読)
🔸 日本語訳をやめる意識を持つ
まず大前提として、英語を聞いたときに**“無意識で日本語に変換している”**ことに気づくことが重要です。
この変換作業が、理解をワンテンポ遅らせ、スピードに置いていかれる原因になります。
英語のままイメージで理解するためには、
🔹「The cat is under the table.」→「猫がテーブルの下にいる」ではなく、“その状況をそのまま頭に描く”
という感覚を育てていきましょう。
🔸 チャンクで理解する力をつける
「get in the car」「at the end of the day」「take it for granted」など、**意味のかたまり(チャンク)**で捉える練習をすると、
1語1語を処理せずに済むため、理解スピードが格段にアップします。
やり方はシンプル:
- よく使われる表現をまとめて覚える
- そのまま口に出して使う(音読・シャドーイングなど)
- 同じ表現がリスニングに出てきたとき、反射的に意味が浮かぶようになる
💡チャンクを増やすだけで、**「あれ?なんか聞き取れるようになった?」**という感覚につながります。
🔸 多聴・多読で「英語のリズムと語順」に慣れる
「英語を英語のまま理解する」力は、理屈だけでは育ちません。
やはり最後は、“大量のインプット”=慣れと感覚が決め手です。
ポイントは:
- 自分のレベルより少し簡単な素材で多聴・多読
- 100%理解ではなく、大意をつかむ練習
- 好きなジャンルや話題のコンテンツを選ぶと、続けやすい
💡ニュース・YouTube・ポッドキャスト・英語学習アプリなど、自分に合う「英語に毎日触れる素材」を持つことがカギです。
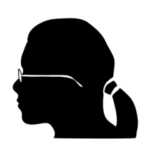
💭 ちなみに、「聞き流し」ってどうなの?と気になった方へ:
👉 英語の聞き流しに効果はあるのか?実は注意が必要な落とし穴と上手な使い方
「ただ聞いてれば英語ができるようになる」はホント?ウソ?
とりしま目線で、やさしく解説してます◎
解決法4|発音と音声変化の理解
「英語の音は聞こえているのに意味が取れない…」
そんな人の多くは、**実は“ちゃんと発音が聞き取れていない”**ことが原因になっています。
英語には、日本語にない“音の変化”がたくさんあります。これらを知らないと、
「知ってる単語なのに聞き取れない」
「ちゃんと発音してるのに通じない」
といった壁にぶつかります。
ここでは、リスニングにもスピーキングにも効く「発音と音声変化」への理解を深める方法を紹介します。
- リエゾンやリダクションなど、音声変化の知識を持つ
- 発音できる音は聞き取れる!自分の発音練習も重要
- 音と文字のギャップに慣れておく
🔸 音声変化とは?まずはルールを知ろう
ネイティブの英語では、単語と単語が自然につながったり、省略されたりします。
代表的なのが以下の3つ:
| 種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| リエゾン | 音の連結 | get it → ゲリッ |
| リダクション | 音の脱落・弱化 | want to → wanna |
| フラッピング | /t/ が /d/ に近くなる | water → ワラー(アメリカ英語) |
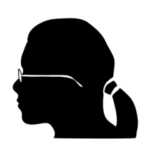
💡これらの変化を知っていると、「聞こえなかった音」が**“聞こえるようになる”**瞬間が増えます。
🔸 発音できる音は聞き取れる
リスニングが苦手な人の多くは、自分が発音できない音を聞き取ろうとしていることが多いです。
英語の発音を練習することで、耳と口のリンクが強化され、「知ってるけど聞き取れない」が減ります。
おすすめは:
- 教材の音声を真似して発音してみる
- AI発音チェックアプリ(ELSA Speakなど)を使ってみる
- 音読やシャドーイングを録音して自分で聞き返す
🔸 音と文字のズレに慣れておく
英語はスペル通りに読まないことが多い言語です。
たとえば:
- knight(騎士):カナイ…? → /naɪt/
- colonel(大佐):コロネル? → /ˈkɝː.nəl/
このギャップが、リスニングを混乱させる原因の1つ。
「英語は音が本体、文字は補助」と割り切って、実際の音ベースで覚える習慣をつけましょう。
解決法5|興味と背景知識を味方にする
リスニング中に「話の流れがつかめない」「言っていることが分からない」というとき、
**“語彙や文法ではなく、背景知識の不足”**が原因になっていることがあります。
また、そもそも興味が持てない内容だと、集中力も続かず、意味を処理する回路が働きにくくなります。
この章では、興味を軸にリスニングの理解力を上げる方法をご紹介します。
- 自分の好きなジャンルを英語で楽しむ(=多聴・多読)
- コンテンツの幅を広げて“背景知識”を積み上げる
- 聞く前に“予測”する習慣をつける
🔸 興味のある題材を選ぶと「英語でも覚えられる」
英語が苦手でも、好きなテーマなら話に引き込まれるものです。
たとえば:
- 海外ドラマ(医療・法廷・恋愛 etc.)
- YouTube(Vlog、料理、DIYなど)
- ポッドキャスト(英語学習・歴史・ビジネス)
- TED Talks(モチベやアイデア系)
自分の好きな分野のコンテンツを英語で楽しめば、
意味が取りやすくなるだけでなく、自然と語彙や表現も増えていきます。
🔸 多様なジャンルに触れて、背景知識を蓄える
知らないジャンルの話が出たとき、理解が止まるのは「語彙不足」だけじゃありません。
“そもそもその話を知らない”=予測ができないというのが、リスニングを難しくする大きな要因です。
だからこそ、いろんなジャンルに触れて、
- ビジネス英語に出てくる用語や構造
- ニュースで使われる定番表現
- TEDやドキュメンタリーに出てくる「ちょっと難しい言い回し」
などをストックしておくことで、「あ、これ前も聞いた」という感覚が増え、意味処理が一気にラクになります。
🔸 聞く前に「こういう話かな?」と予測する癖をつける
英語を聞くときに、「この話、何についてかな?」と予測しながら聞くだけで、理解の精度は大きく変わります。
これは、背景知識があるからこそできる技。
前後の情報や話し手のトーンから、
「この後こういう話が来そう」→「やっぱりそうだった」
という**“文脈処理のスキル”**が身についていくんです。
💡ニュースやTEDなどの「話の構成が明確な素材」で練習すると効果的です。
🛠️ 今回ご紹介したような、音読・シャドーイング・ディクテーション・オーバーラッピングといったトレーニングを、
実は1つのアプリ内でまるっと実践できるサービスもあります。
🎧 それがTORAbit(トラビット)
![]() 。
。
実際にちゃっちゃんが使ってみたレビューはこちら:
👉 【体験レビュー】トラビットのシャドーイング機能、正直どう?
「もうトレーニング内容はわかったから、とりあえず試してみたい」という方はこちらからどうぞ:
👉 TORAbitを見る
![]()
まとめ|「聞こえるけど分からない」は“次のステージ”へのサイン
「英語の音は聞こえるのに、意味がスッと入ってこない」――
この悩みは、決してスキル不足ではなく、“理解力の地盤”を整えるべき時期に来ている証拠です。
語彙・文法・音声変化・処理スピード・興味のある内容…
それぞれの要素を少しずつ整えていくことで、
英語が「音」ではなく、「意味」として自然に入ってくる感覚が育ちます。
焦らなくて大丈夫。“意味が取れない”は、伸びている途中にだけ起こることです。
毎日の中に、音と意味を結ぶ練習をコツコツ積み重ねていきましょう。
🚀 次のステップへ進みたい方へ
もしあなたがすでに「音は拾えている。でも…話の流れや意図がつかめない」と感じているなら、
次は「聞こえるけど“深く理解できない”という壁」を越えるステージに来ているのかもしれません。
そんな方には、以下の記事もおすすめです:
👉 [内容は聞き取れるのに理解ができない…リスニング上級者の“見えない壁”の正体とは?(※近日公開予定)]