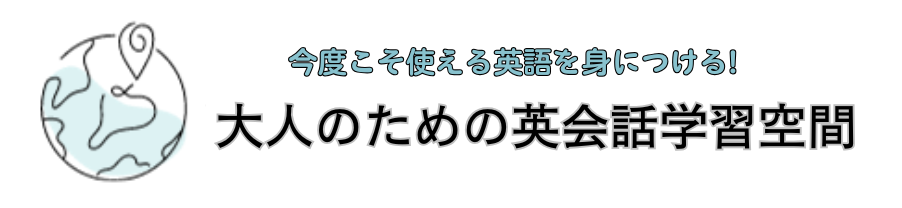USCPAの選択科目(BAR・ISC・TCP)は、単なる試験対策ではなく、取得後のキャリアや年収レンジを大きく左右する“専門性の分岐点”です。
特に読者が気になるのは、
「このデータってどこから来ているの?」という点だと思います。
ここでは、この記事で扱う統計情報やキャリア情報の主な情報源について、最初に明確にしておきます。
まず、USCPA取得者の年収やキャリア変化に関する具体的な統計データ(たとえば「年収1,000万円以上が60.5%」「取得後71.1%が年収アップ」など)は、国際資格専門校アビタス(Abitus)が実施した卒業生調査が中心となっています。最も詳細でアクセス可能な統計データであり、多くの日本在住USCPA取得者の実態を反映しています。
一方で、試験制度、選択科目の合格率、スキルレベル、試験構造などの客観的なデータは、AICPA/NASBA(全米州政府会計委員会)が公表している公式データを基にしています。
また、BIG4コンサルティングファームの年収水準、外資系企業の給与レンジ、IT監査・国際税務などの職種別年収は、マイナビ会計士、士業コラム、Big4関連の独立記事、予備校情報など、複数の外部情報源から得られた内容を総合して掲載しています。
この記事の情報源は大きく2種類
【1】アビタス(Abitus)に基づく情報
・USCPA合格者の年収帯(例:60.5%が年収1,000万円超)
・取得後のキャリア影響(年収アップ・社内評価の向上)
・ISC/IT知識の重要性に関する解説
・日本在住合格者の78.5%がアビタス卒業生というデータ
・アビタスが提供する3選択科目(BAR/ISC/TCP)への対応状況
【2】AICPA/NASBAおよびその他の独立ソースに基づく情報
・新試験制度の構成(必須3科目+選択1科目)
・各科目の最新合格率(BAR 43%、TCP 78% など)
・Blueprintで定義されたスキルレベル(ISCは「記憶と理解」が最多)
・Big4コンサルの年収(入社10年目1,300万〜2,000万円)
・外資系・金融・監査法人の年収相場
・TACなど他予備校の科目戦略(例:TCP推奨)
・USCPAの米国平均年収(約92,000ドル=約1,400万円)
つまり、試験制度や科目難易度はAICPA/NASBAの公的データを基礎に構成し、
資格取得後の年収やキャリア変化の“実態データ”はアビタス卒業生調査が中心です。
この記事は、これら複数の情報源を重ね合わせて、
「選択科目によってキャリアと年収がどう変わるのか?」をわかりやすく整理してみました。
USCPAの選択科目でキャリアが変わる!BAR・ISC・TCPの特徴と年収を徹底比較
USCPAは「取ったら終わり」の資格ではありません。
どの選択科目(BAR・ISC・TCP)を選ぶかで、将来のキャリアと年収レンジが大きく変わります。
2024年から始まった新試験制度で選択科目が導入されたのは、受験生をより専門的で市場価値の高い人材にするためです。
つまり、選択科目は“あなたがどのプロフェッショナルになるかの分岐点”。
USCPAの新試験制度と“選択科目でキャリアが分かれる理由”
USCPAは必須3科目(FAR・AUD・REG)で基礎能力を固め、選択科目で専門性をカスタマイズする仕組みです。
- BAR … 財務・管理会計・経営分析をさらに深める
- ISC … IT監査・内部統制・情報セキュリティを伸ばす
- TCP … 税務の応用を武器にする
この3科目は、どれを選ぶかで採用されやすい業界・職種・年収が変わるほど影響が大きい科目です。
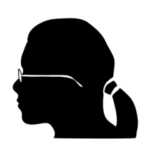
CPAと一言で言っても専門分野が分かれてくる、そのための深い知識が業界や年収を分ける、ということです。
AI・自動化が進んで、単純な仕訳・財務処理はどんどん機械化したことによって、会計“だけ”できる人の価値が相対的に下がった、というリアルが背景にあります。
採用側はUSCPAの選択科目をどう評価しているのか?
USCPAの選択科目(BAR・ISC・TCP)は、受験生から見ると「どれを選ぶかの分岐点」に思えるかもしれませんが、実はこの仕組みは**採用する側の企業ニーズをダイレクトに反映した“専門性のシグナル”として機能しています。
企業・監査法人・コンサルティングファームは、もはや「会計ができるだけの人材」を求めていません。AIによる自動化が進み、一般的な会計処理や監査手続きは標準化が進んでいるため、採用側が欲しいのは “会計+もう一つの専門性を持つ人材” です。
選択科目はまさにその「もう一つの専門性」を示す指標になっており、採用担当者は以下のように評価します。
1. BARを選んだ人への評価
BAR(ビジネス分析・報告)は、財務会計・管理会計・企業価値評価などを深めた科目です。
企業側から見ると、
- 「財務・経営分析ができる人材」
- 「FP&Aや経営企画で活躍できる即戦力」
- 「事業会社の管理職候補」
と評価されます。
特に外資系企業やPEファンド、M&A領域では高く評価され、経理部門からCFO候補のルートにつながりやすいのが特徴です。
2. ISCを選んだ人への評価
ISC(情報システムと統制)は、IT監査・セキュリティ・内部統制に特化した科目。
採用側はこう受け取ります。
- 「会計×ITの希少スキルを持つ人材」
- 「IT監査やDX推進に即投入可能」
- 「内部統制領域で強く、監査法人でも需要が高い」
近年は会計業務の自動化が急速に進んでいるため、ISCは特にBIG4監査法人のリスクアドバイザリー部門やIT監査部門で評価が高く、市場価値が今後最も伸びる領域と見なされています。
3. TCPを選んだ人への評価
TCP(税務)を選んだ場合、採用側はこう評価します。
- 「国際税務を理解し、専門性が高い」
- 「BIG4 Tax、税理士法人の即戦力候補」
- 「多国籍企業の税務部門の適性が高い」
日本企業では国際税務が慢性的に人材不足のため、TCP選択者はキャリアの出口が明確で転職に強いと見られるのが大きな利点です。
採用側が専門性を求める理由
企業ニーズが専門特化に変わった理由は、以下の3つが大きいです。
- 会計業務の自動化・標準化により、ジェネラリストの価値が低下した
- 事業会社・外資系では、財務・IT・税務のプロフェッショナルが不足している
- 採用時に「何ができる人なのか」を科目で判断しやすい
AICPA自体が企業ヒアリングを行い、「会計士に求められるスキル」を集約した結果として、BAR/ISC/TCPの3科目が生まれています。
つまり選択科目制度は、雇用側の声を資格制度に反映させたものと言えます。
選択科目3つの違いをまず整理
| 科目 | 主な特徴 | 得意分野 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| BAR | 財務会計・管理会計・経営分析を深める | 財務分析、原価計算、経営企画 | 経理・財務でキャリアアップしたい人、CFO候補 |
| ISC | IT監査・情報システム統制・セキュリティ | IT統制、DX、サイバーリスク | 会計×ITの希少スキルを身につけたい人、IT監査志望 |
| TCP | 税務の応用・国際税務に直結 | 国際税務、税務コンプライアンス | BIG4 Tax志望、国際税務で年収を伸ばしたい人、最短合格狙い |
選択科目別|科目内容×難易度×合格率まとめ
USCPAの選択科目(BAR・ISC・TCP)は、それぞれが「必須科目の発展版」でありながら、難易度・合格率・必要なスキルレベルが大きく異なります。まずは3科目を一歩引いて比較することで、自分がどの分野に適性があるのか、そしてどの科目がキャリアの方向性に合っているのかを把握しやすくなります。
選択科目は“どれが簡単か”だけで決めるのではなく、科目の性質・試験傾向・専門領域の違いを理解した上で選ぶことが、後悔しない科目選びにつながります。ここでは、最新の合格率データとスキルレベルを踏まえて、3科目の特徴を比較できるように整理しました。
BAR(最難関)
合格率:約43%(2025 Q3)
財務会計のディープな領域、M&A、企業価値評価など“ガチ難”の科目。分析力と応用力が問われるため、3科目の中で最も難しい。
ISC(易しめ)
合格率:約68%(2025 Q3)
ITに抵抗がなければ最も取り組みやすい。
記憶中心の問題が多く、“勉強したら点が取れる”タイプ。
TCP(最も易しい)
合格率:約78%(2025 Q3)
選択科目の中で唯一70%台後半。
REGの延長線で理解しやすく、最短合格を狙う層が殺到。
選択科目別|キャリアパスと想定年収比較
選択科目を理解したら、次に気になるのが「この科目を選ぶと、どんな働き方ができて、どれくらいの年収が狙えるのか?」という具体的なキャリアの話です。
USCPAの選択科目は、単なる試験の分岐ではなく、企業が求める専門性そのものを反映しています。
BAR・ISC・TCPは、それぞれが異なる職種・業界に直結しており、選んだ科目によって“入りやすい分野”も“伸ばしやすい年収帯”も大きく変わります。
ここでは、採用側がどのように評価しているかを踏まえながら、3科目がどのキャリアへつながり、どの程度の収入が期待できるのかを具体的に比較していきます。
BAR(財務・経営分析・CFO候補の道)
こんな人に最適:
・財務/会計が好き
・CFO/FP&A/経理部長を目指したい
・事業会社でキャリアアップしたい
代表的キャリア
・経理/財務(財務会計・管理会計)
・FP&A(財務企画)
・経営企画
・財務アドバイザリー(FAS/M&A)
年収レンジ(日本)
・経理/財務マネージャー:700〜1,200万円
・FP&A/経営企画:800〜1,500万円
・財務コンサル:1,000〜2,000万円
ポイント
事業会社でのキャリアアップに直結し、CFO候補を目指すならBAR一択。
ISC(IT監査・DX・内部統制の専門家の道)
こんな人に最適:
・ITと会計の両方に興味
・監査法人でIT監査に進みたい
・DX/サイバーセキュリティの分野で稼ぎたい
代表的キャリア
・IT監査
・内部監査/内部統制
・システムリスクコンサル
・データマネジメント/ITガバナンス
年収レンジ(日本)
・IT監査(Big4):1,000〜1,300万円
・内部監査室(事業会社):800〜1,200万円
・データマネージャー:900〜1,400万円
ポイント
「会計×IT」という超希少スキルで市場価値が爆上がり。
今後10年伸びるのはこの分野。
TCP(国際税務・BIG4 Taxの道)
こんな人に最適:
・税務が得意
・国際税務で稼ぎたい
・早くUSCPAを取りたい
代表的キャリア
・税理士法人(国際税務)
・BIG4 Tax
・多国籍企業の税務部門
年収レンジ(日本)
・国際税務コンサル:900〜1,500万円
・BIG4 Tax マネージャー:1,000〜1,600万円
・企業税務部門:700〜1,200万円
ポイント
求人需要が高く、専門性が明確で転職に強い。
どの選択科目があなたに最適か?タイプ別診断
財務・分析が好き → BAR
ITリテラシーあり → ISC
最短合格+国際税務 → TCP
とりしまの考察

昨今の世界情勢から経済の動きの変動がものすごい速さで変化しているのが見てとれます。USCPAは会計ができる人、だけではなく、「その分野に詳しい専門家」という地位を確立していることは確かですね。
どの分野を選ぶかはもちろんあなた次第です。色々な理由で選択することとなるでしょう。
けれどもし今、「どの科目も大事に見えて決められない…」と感じているなら、それは自然なことです。BAR・ISC・TCPはどれも専門性が高く、キャリアの出口も広いからこそ、迷うのは当たり前。
ただし、1つだけ覚えておいてほしいのは、今完璧な答えを探す必要はないということです。
選択科目は、“いまのキャリアに合わせる”ことも、“これから伸ばしたい強みを選ぶ”ことも、どちらも正解です。むしろ、大切なのは「自分がどんな働き方をしたいか」という方向性を決めることで、科目の選択はその結果として自然に決まります。
もし現時点で方向性が曖昧でも心配いりません。学習を進める中で「この領域が面白いかも」と感じたタイミングで決めても遅くないし、実際に多くの合格者がそのスタイルで成功しています。
焦って選ぶ必要はありません。
あなたのキャリアの軸が見えたとき、選択科目は“選べるようになる”ものです。
そのタイミングを信じて、一歩ずつ前へ進んでください。
USCPA取得後の年収アップの現実
アビタス調査によると:
・USCPA取得者の60.5%が年収1,000万円以上
・71.1%が資格取得後に年収アップ
・Big4/外資/コンサルでは年収1,300〜2,000万円
USCPAを武器にすると、キャリアと年収のジャンプ幅は大きい。
まずは情報収集から始めよう
結論|選択科目は「キャリアの出口」を決める最重要ポイント
BAR・ISC・TCPは、単なる試験科目ではなく、
将来の働き方・職種・年収レンジを決める“キャリア分岐点”。
・事業会社で管理職→BAR
・DX/IT監査で稼ぐ→ISC
・税務で高収入→TCP
この3つの道は、どれも年収1,000万円超えが現実的。
あなたがどの専門家になりたいかで、選ぶべき科目は自然に決まっていきます。